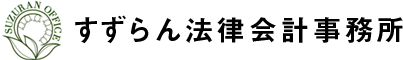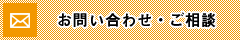一口法律豆知識
~目次~
交通事故の争点
| ① 過失相殺 |
| ② 損害 |
| ③ 損害賠償請求の相手方 |
| ④ 後遺障害 |
| ⑤ 実務上問題になることの多い損害 |
遺言
| 自筆証書遺言、公正証書遺言どちらがおトク?? |
離婚
| ① 離婚手続きについて |
| ② 離婚時の財産分与と養育費 |
| ③ 財産分与のQ&A |
借地について
| ① 借地権とは?? |
| ② 事業用定期借地契約 |
賃貸借契約
| ① 賃貸借契約時における原状回復義務 |
| ② 立退料の相場 |
~交通事故の争点①~過失相殺~
1 過失相殺とは
交通事故が発生した場合、加害者側だけでなく、被害者側にも多少の原因(過失)がある場合も少なくありません。そのような場合に、加害者側に一方的に事故の全責任を負わせるのは、必ずしも公平とはいえないと考えられます。
過失相殺とは、『ある交通事故が発生した場合に、当該事故の原因となった当事者双方の過失の程度に従って、事故の責任割合(過失割合)を定め、当該割合に応じて損害賠償の範囲を制限しようというもの』です(例えば、事故によって、被害者に100万円の損害が発生した場合でも、被害者側自身の過失が5割ある場合は、加害者には50万円しか請求できないことになります)。
2 過失相殺が問題となる理由
では、このような過失割合は、どうやって決まるのでしょうか。
多くの場合は、当事者間で交渉して過失割合について合意するか、合意ができなかった場合は、裁判所によって事故態様をもとに客観的に判断してもらうことになります。
過失割合に関する考え方は、人によって様々というのが実情です。例えば、同じ交通事故であってお、人によって過失割合に関する評価が大きく異なるということも、実はそれほど珍しいことではありません。
過失割合に関しては、裁判所自身が、過去の事例を整理し、交通事故の類型ごとの基準を公表しており、これが最も有効な判断資料となっています。もっとも、全く同じ事故というものは存在しない以上、場合によっては、このような基準がほとんど、あるいはまったく判断資料として機能しないこともあり得ます。
このように、交通事故紛争においては、しばしば当事者間の具体的な過失割合を巡って問題が生じるのです。
3 過失相殺が問題となったら
もし皆様の誰かが、交通事故の当事者となり、過失割合が問題となってしまった場合は、裁判所が公表している基準を参考にしてみてください。当事者でうまく解決できない場合は、弁護士にご相談いただくのもの有効な方法です。
~交通事故の争点②~損害~
もしも皆様が交通事故の被害に遭われた場合、加害者に対し、過失割合にしたがった損害の賠償を請求することになります。
ここで、相手方に賠償を請求することのできる「損害」には、どのようなものあるがあるでしょうか。
1 物的損害
自動車修理費・代車費用・評価額(いわゆる格落ち)・レッカー費用等、交通事故によって「物」が損傷した場合に発生する損害です。
なお、裁判所は、物的損害の場合には原則として慰謝料請求(例えば、愛着のある「物」が壊れてしまったことによる精神的苦痛の賠償請求)を認めてくれません。
2 人的損害
人的損害は、交通事故によって「人」が傷害を負った場合に発生する損害で、さらに積極損害と消極損害に分類されます。
(1)積極損害とは、治療関係費・入院雑費・入院費のための交通費・付添看護費・将来の看護費・装具や器具等の購入費・家屋などの改造費・葬儀関係費等、交通事故によって被害者が出費を余儀なくされるものをいいます。
(2)消極損害とは、休業損害・後遺症による逸失利益・死亡による逸失利益・入院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料等、事故に遭わなければ将来得ることのできた利益の喪失をいいます。
3 損害の有無・範囲
これらの損害は、交通事故と関連性(相当因果関係)のある範囲で損害として認められることになりますが、実際は事故との関連性が認められるか否か等について当事者間で意見がまったく異なる場合も少なくありません。
また、消極損害は、損害の内容が抽象的であるため、物的損害や積極損害に比べて、事故との関連性の認められる範囲が問題となることが多いといえます。
以上のように、一口に「損害」といっても、その内容は非常に多岐にわたることになります。さらに、上記で列挙した損害項目はあくまでも実務上よく発生するもの、問題となるものを例示しているにすぎず、現実の交通事故では、上記に当てはまらない損害が問題になることも多くあります。
当事務所では、例えば事故の被害に遭われた皆様が加害者に賠償を求める場合に生じる「これは損害として認められるのかな?」、「この損害に関する加害者の言い分は妥当なのだろうか?」といった疑問に、過去の裁判例等に照らした適切なアドバイスをさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
~交通事故の争点③~損害賠償請求の相手方~
交通事故の被害にあった方は、誰に対して、損害賠償を請求できるのでしょうか。
事故の当事者である加害者本人に請求できるのはもちろんですが、場合によっては、法律の規定により、加害者以外にも損害賠償請求できる場合があります。
以下では、直接の加害者以外の者に賠償責任が発生する典型的な場合についてご説明したいと思います。
1 運行供用者の責任
自動車損害賠償保障法3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者と呼ばれます。)は、その運行によって他人に人的損害を賠償する義務がある」旨規定しています。
例えば、自動車の借主が事故を起こした場合の貸主である所有者などが運行供用者に該当し、損害賠償責任を負うことがあります。
もっとも、運行供用者という概念は、必ずしも明確ではありませんので、実務では、運行供用者に該当するか否かがしばしば争いになります。
2 監督義務者の責任
加害者本人に責任能力がない場合、加害者本人は損害賠償責任を負わず、代わって監督義務者が責任を負います(民法714条1項)。
責任能力とは、事故の行為の責任を弁識する能力をいいます。裁判では、小学生くらいまでの未成年者は、責任無能力者にあたるとされることが多いようです。
なお、加害者に責任能力があれば、未成年者であっても不法行為責任を負い、親権者は原則として賠償責任を負うことはありません。もっとも、親権者に監督義務違反があり、当該監督義務違反と損害の発生との間に関連性(因果関係)が認められるのであれば、親権者も損害賠償責任( 民法709条)を負うことがあります。
3 使用者の責任
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について被害者に加えた損害を賠償する責任を負います(民法715条1項)。
例えば、従業員が社用車で取引先に移動している際に事故を起こしたような場合、雇用主は従業員と共に損害賠償責任を負うことになります。
実務上は、従業員が私用で社用車を運転して事故を起こしたような場合などに、事業の執行に該当するか否かが争われることがあります。
*複数の相手方に賠償請求できるということは、例えば、加害者の一人に資力がなく、賠償能力が不安視される場合などに意味があります。
~交通事故の争点④~後遺障害~
交通事故によって傷害を負った場合、当該傷害が治療によって完全に回復(治癒)するに越したことはありませんが、残念ながら完全には回復せず、何らかの症状が残ってしまう場合があります。
このような場合、残存症状の程度によっては、後遺障害が問題となることがあります(以下、事故により後遺障害が残った方を「被害者」、相手方を「加害者」といいます。)
1 後遺障害とは
後遺障害とは、症状固定時(治療を継続しても症状改善の見込みがなくなったとき)に残った精神的・身体的な毀損状況をいいます。後遺障害の有無・程度について、実務上は、通常『後遺障害等級表』に当てはめて認定されます。
『後遺障害等級表』とは、具体的な症状を列記し、これらを程度の重いものから順に1級~14級の等級に分類したものです。例えば、事故によって局部に神経症状が残ってしまった場合(むちうち症など)は第14級に該当することになります。
2 後遺障害が残った場合の問題点
不幸にも被害者に後遺障害が残ってしまった場合、これに対応する損害の賠償を求めることになります。具体的には、①後遺障害慰謝料、②後遺障害逸失利益が問題となります。
- ① 後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことにより、被害者に生じた精神的苦痛を填補するものです。
具体的な損害額については、もちろん事案ごとに判断されることにはなりますが、実務上は後遺障害の等級に応じて基準となる金額が定められています。
- ② 後遺障害逸失利益
後遺障害が残った場合、一定の割合で被害者の労働能力が失われることになります。後遺障害逸失利益は、このように労働能力が低下したことによる将来の収入額の減少を填補するものです。
後遺障害逸失利益の算定にあたり、実務上は算定式に当てはめて計算します(例えば、有職者の場合:基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)が、個々の事案を具体的に算定式に当てはめるにあたって紛争が生じることが少なくありません。なお、現実には被害者に減収が発生していない場合は、当該後遺障害の程度・被害者が従事する職業の性質・減収が発生していない理由等によっては、逸失利益が認められないとされる場合もあります。
また、保険会社が提示する算定額は、裁判所の算定基準に比べて低額のことが一般ですので後遺障害が残るような怪我を負った場合は、一度弁護士に相談されるのが良いと思います。
~交通事故の争点⑤~実務上問題になることの多い損害~
後遺障害に関する損害(後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益)以外に、実務上問題となることが多い損害項目についてご説明いたします。
1 休業損害
休業損害は、障害が治癒(又は症状固定)するまでの間に、被害者が治癒・療養のために休業又は不十分な就業を余儀なくされたことによって発生する収入減少額として把握するものです。
休業損害の具体的な算定方法について、休業によって現実に喪失した金額がわかる場合はその金額となります。他方、休業によって現実に喪失した金額が判明しない場合は、1日当たりの収入額に相当な休業期間を乗じて算定されることになります。
このような休業損害については、算定の前提となる項目、すなわち1日当たりの収入額(基礎収入額)や相当な休業期間をどのように認定するかについて、当事者間で見解が相違する場合が少なくありません。例えば、被害者が会社役員の場合、基礎収入として認定されるのは役員報酬の一部(労務対価部分)とされていますが、どのように労務対価部分を考えるのかについては明確な基準がないため、当事者間で揉めることがあります。
2 入通院慰謝料
入通院慰謝料は、事故によって傷害を受けた者が被った精神的損害(苦痛)を填補するものです。
入通院慰謝料の具体的な算定方法について、実務上は、①自賠責保険基準(自動車損害賠償保障法によって設定された基準)、②任意保険基準(各保険会社が独自に設定している基準)、③③弁護士基準(裁判基準)(過去の裁判例をもとに、財団法人日弁連交通事故相談センターが設定している基準)という異なる3つの基準が用いられています。そのため、全く同じ事例であっても、いずれの基準を採用するかによって慰謝料額は異なってきますし、場合によっては数十万円単位で差異が生じることもあります(一般的には、弁護士基準を用いたほうが、自賠責保険基準や任意保険基準を用いた場合よりも慰謝料額は大きくなります。)。 示談交渉の際、加害者側は、例えば①自賠責保険基準や②任意保険基準を用いて入通院慰謝料額を算定するなどして、少額の損害賠償額による示談を提案してくる傾向があります。被害者としては、安易に加害者側の提案を信じるのではなく、疑問があればご自身で調べるなり弁護士に相談されるなりして、提示された金額の相当性を吟味して示談することが大切です。
~自筆証書遺言、公正証書遺言どちらがおトク?~
自筆証書遺言と公正証書遺言どちらでした方がいいですか?とよく訊かれます。
遺言は様式行為とされ、一定の方式でなされたものでないと効力がないとされています。一般には、このどちらかの方法で遺言書を作成しています。自筆証書遺言は、全文と日付及び氏名を自分で書き、印を押す必要があります。公正証書遺言は公証人に作成してもらいますので、公証役場に行って作成するのが原則です。
自筆証書遺言は、簡便で費用も掛からないのが長所ですが、検認という手続きを経る必要があること、不適式だとして無効になったり、意図した効力を発揮しない場合があるのが短所です。最近も夫が愛する妻のために自筆証書遺言を残したが、登記官から不動産の記載に不備があるとされ、登記ができなかった事案を経験しました。
これに対し、公正証書遺言は、検認の必要がありませんし、公証人のチェックを受けているので、効力や記載内容が問題となることはほとんどないのが長所です。ただ、証人二人の立ち合いが必要となる等少し手続きが煩雑なのと相続財産の額に応じた費用を納める必要があるのが短所です。遺言書の内容を書き換えることはないと考えるなら、多少費用が掛かっても公正証書遺言が無難だと思います。
~離婚手続きについて~
離婚をする場合、①財産分与、②慰謝料、お子さんがいらっしゃる場合には③親権者、④養育費という問題についてどのようにするかを決める必要があります。
まずは夫婦間でこれらの問題について話し合いをしていただき、うまくまとまれば離婚が成立します(協議離婚)。離婚時に約束したことが後から守られなくなってしまうこともありますので、夫婦間で決めたことを公正証書にしておくことをおすすめします。
夫婦の一方が離婚に応じない場合や、上述した①から④について夫婦間の協議が整わなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります(調停離婚)。裁判所では、裁判官に代わって調停委員(通常男女各1名)が、夫婦相互に話を聞きながら話し合いの手助けをします。裁判所に、当事者同士が会わないよう配慮していただくことも可能です。
ただ、調停も、あくまでも話し合いの場ですので、まとまらない場合は不成立となります。その場合は、家庭裁判所が、調停に代わる審判によって離婚させた方がよいと判断すると、審判を行います(審判離婚)。
また、調停が不成立となった場合や、審判に不服がある場合には、訴訟を提起し、裁判によって離婚ということになります(裁判離婚)。
審判離婚は、当事者の一方に不服があれば訴訟に移りますので、それ程多くはありません。
いずれにしても、お互いの幸せとは何か、お子さんにとってどうすることが幸せか、じっくりと考えていただいた上で、離婚の手続きを進めていただければと思います。
~離婚時の財産分与と養育費~
離婚をする場合、財産分与、慰謝料、お子さんがいらっしゃる場合には養育費をどうするか、というお金にまつわることを決めなければなりません。
上述したとおり、これらの問題をどう決めるかは当事者の自由ですので、夫婦間の話し合いで合意できれば、特に問題はありません。しかし、夫婦間で折り合いがつかない場合、裁判所は以下のような考え方のもとに具体的な金額を決めています。今回は、財産分与と養育費についてお話したいと思います。
1 財産分与について
夫婦が離婚する場合、夫婦が婚姻中に形成した共有財産(婚姻前に蓄えた預貯金や婚姻前に相続や贈与により得た財産は含みません。)は、夫婦が協力して形成されたものとして、相互に2分の1の権利を有するとされています。
裁判所は、この考え方を原則として、離婚後の扶養や慰謝料等の要素を考慮して具体的な財産分与の方法を決めます。
2 養育費について
養育費とは、子どもが独立して社会人として自立するまでに要する費用(子どもの衣食住の費用、教育費、医療費等)をいいます。子どもが成人に達するまでとするのが原則ですが、最近では、大学に進学される方も多いので、大学卒業までとされるケースも増えています。
裁判所においては、具体的な養育費の金額の算定にあたり、裁判官を中心にして作成された養育費算定表が用いられます。これにより、夫婦双方の収入金額(年収)、子どもの人数と年齢を基準にして、2万円(所得が低い場合は1万円)の幅のある養育費を算定することができます。
例えば、夫の年収が500万円、妻の年収が100万円、妻が子ども2人(第1子が15~19歳、第2子が0~14歳)を引き取る場合、算定表によれば、夫が妻に支払うべき養育費は、6万円から8万円となります。
養育費算定表は、裁判所のホームページにも掲載されておりますので、参考にされたい方はアクセスしてみてください。
~財産分与のQ&A~
今回は、離婚時の財産分与について、よく質問される内容をQ&A形式でまとめてみました。
| Q1 | こ相手方が管理している財産があるはずですが、詳細がわかりません。どうしたらいいでしょうか。 |
| A1 | 相手方名義の銀行預金等があるにもかかわらず、相手方が開示しない場合、弁護士による照会手続や調停段階では家庭裁判所における調査嘱託手続等を利用して、金融機関等に対して調査を依頼することができます。ただし、金融機関等が特定されていないと手続をとることができません。そして、何も証拠がないまま、「あるはずです」と主張するだけでは財産分与の対象にはなりません。したがって、財産分与を正確に行うためには、事前に夫婦の財産を把握しておくことが望ましいといえます。 |
| Q1 | 別居時には預金が500万円ありましたが、1年後に離婚の話し合いをしようとしたら250万円になっていました。財産分与の対象となる預金はいくらになるのでしょうか。 |
| A1 | 財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻生活中に協力して築いた財産をいい、別居中の財産の増減は考慮されません。したがって、別居時の財産、すなわち500万円の預金が財産分与の対象となります。 |
| Q1 | 婚姻後、夫名義で自宅マンションを購入しましたが、住宅ローンが残っております。どのように財産分与をすればよいでしょうか。 |
| A1 | まず、マンションの名義がどちらのものであれ、財産分与の対象となります。そして、マンションの取得者、今後の居住者、残ローンの負担割合については、夫婦間で調整し、話し合いで解決することになります。 ①不動産の価額から残ローンを控除してプラスであれば、取得者が他方にプラス分の2分の1を支払い、残ローンを負担する、②オーバーローンの場合はI )マンションを売却してローンを2分の1ずつ負担する、Ⅱ)一方が取得・居住してローンを負担する等様々な方法が考えられ、今後の夫婦の生活スタイルや他の財産との兼ね合いその他事情を考慮して決めることになります。 |
~借地権とは??~
「借地権」という言葉を聞いたことがあると思います。しかし、借地権がどのような権利なのか、正確には知らない方がほとんどだと思います。私は、主に地方自治体の職員の方を対象として「公共用地の取得」、「区画整理」について年に数回講義をさせていただいていますが、土地の取得を業務内容としている職員の方でも、「借地権」の法的意味を正確に知っている方が少なくて驚きます。
「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権又は賃借権をいいます。地上権が設定されることは少ないので、賃借権が問題となります。借地権は、建物の所有を目的とする土地の賃借権ですから、駐車場として借りているような場合は、借地権は成立しません。また、親から土地をタダで借りて家を建てているような場合は、使用貸借関係になりますので、借地権が成立しません。借地権が成立しない場合は、新たに土地を取得した第三者に対抗するためには、借りている本人名義で建物の登記をしておく必要があります。借地借家関係はトラブルになると大変ですので、事前に当事務所にご相談ください。
~事業用定期借地契約~
借地権が設定されると、借地権者は強い権利を持つことになりますが、反面、地主さんは、土地の返還を求めることが困難になり、土地活用を阻害する側面があります。そこで、借地借家法には、期間がきたら返還してもらうことができる借地契約の類型が規定されています。
その中の一つに、事業用定期借地契約があります。これは、もっぱら事業用の建物を建てることを目的として土地を賃貸する契約です。契約期間は、以前は10年以上20年未満でしたが、現在は10年以上50年未満の間の確定期限となっています。この事業用借地契約には、通常の借地契約を異なり更新、建物の滅失・再築による解約、建物買取請求権は認められていませんので、契約期間が到来すれば建物の存続いかんにかかわらず、明け渡しを求めることができます。期間が10年以上30年未満の事業用定期借地契約には、更新後の建物再築の許可の規定の適用もありません。この契約は、公正証書で行う必要があります。
ある程度まとまった空き地を持っていて当分利用を考えていない方は、事業用建物の使用のために土地を貸すことも考えてみたらいかがでしょうか。
~賃貸借契約終了時における原状回復義務~
さて、今回からは、賃貸借契約における諸問題についてお話ししたいと思います。初回は、貸主側、借主側、どちらからも特によくご相談を受けることのある、マンション等の賃貸借終了時における原状回復について取り上げます。
賃貸借契約が終了すると、借主は、貸主に対し建物を原状に戻して返還しなければなりません(これを、「原状回復義務」といいます。)。では、原状回復しなければならない範囲・程度については、どのように考えるべきなのでしょうか。
原則としては、以下のように考えられています。
まず、借主が、故意・過失により住宅を毀損、滅失した場合は、借主の責任によるものなので、借主が補修して原状に戻さなければなりません。
一方、借主の故意・過失なく、通常の使用をしていても自然と汚れ、損耗する部分(例えば、入居年数とともに自然と変色する畳や壁紙などが挙げられます。これを「通常損耗」または「自然損耗」などといいます。)については、原則として原状回復の範囲に含まれず、貸主の負担で補修すべきとされています。
では、契約書において、「通常損耗についても借主負担で原状回復しなければならない」との特約が定められていた場合はどうでしょうか。このような特約に関して、判例は、通常損耗についても借主の負担とするには、少なくとも、借主が費用を負担することになる通常損耗の範囲が契約書の条項自体に具体的に明記されているか、あるいは、貸主が口頭により説明し、借主がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められなければならないとしています。したがって原状回復に関する特約が定められている場合は、契約書の内容を確認する必要があります。
具体的にどこまで原状回復をしなければならないかについては、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を発表しておりますので、興味のある方は同省のホームページをご参照ください。
~立退料の相場~
賃貸借契約に関わる問題の中で、ご相談が多いテーマの1つに、「立退料」があります。今回は「立退料」についてお話したいと思います。
<立退料とは>
賃貸借契約においては、契約書上、賃貸借期間が終了しても、自動で更新する旨の合意が定められていることが多いですが、そのような合意がない場合でも、法律上、当事者が「更新拒絶」をしない限り更新されるとみなされます。
そして、貸主による「更新拒絶」が認められるためには、①期間が満了する1年前から6か月前までに、借主に対して更新拒絶の通知をすること、②正当事由が認められることが必要とされています。
正当事由は、不動産の貸主・借主が不動産の使用を必要とする事情、契約締結に至る事情や賃料支払状況などの従前の経過、不動産の利用状況及び現況(建物の場合建替えの必要性など)などによって判断されますが、その他に、貸主が借主に対し、相当額を支払うことで正当事由が補完され、貸主による更新拒絶が認められる場合があります。この相当額を「立退料」といいます。
<立退料の相場>
では、「立退料」の相場はどのくらいなのでしょうか。
「立退料」は、あくまでも正当事由を補完するために支払うものですので、具体的な事情によって異なり、明確な基準はありません。 ただ、裁判になった場合には、次の①~③のような事情を考慮して判断されます。借主に立退きを求めることを検討されている方はご参考にしてみて下さい。
- ①立退きにより借主が支払わなければならない移転費用の補償(引越費用、移転先取得のための費用(敷金、権利金、不動産業者への仲介手数料、従前賃料と移転先賃料との差額))
- ②立退きにより消滅する利用権(借地権・借家権)の補償
- ③立退きにより借主が事実上失う利益(居住権、営業権)の補償